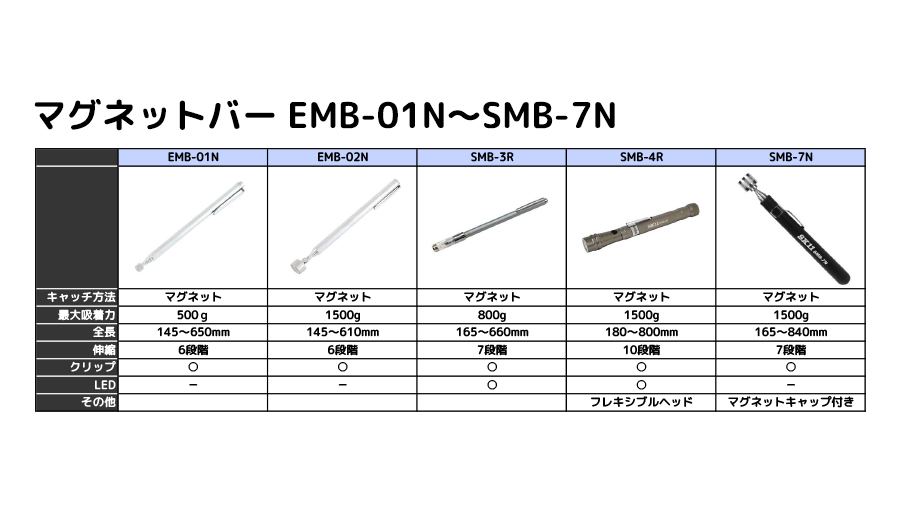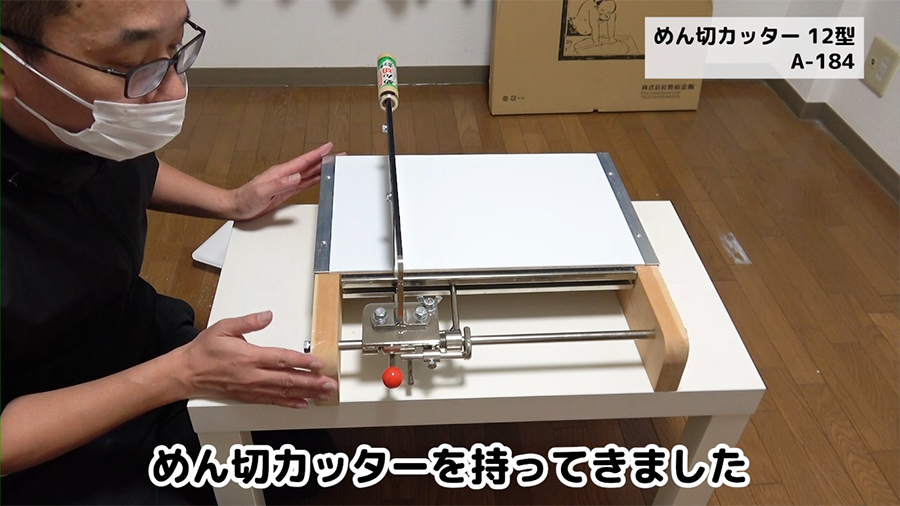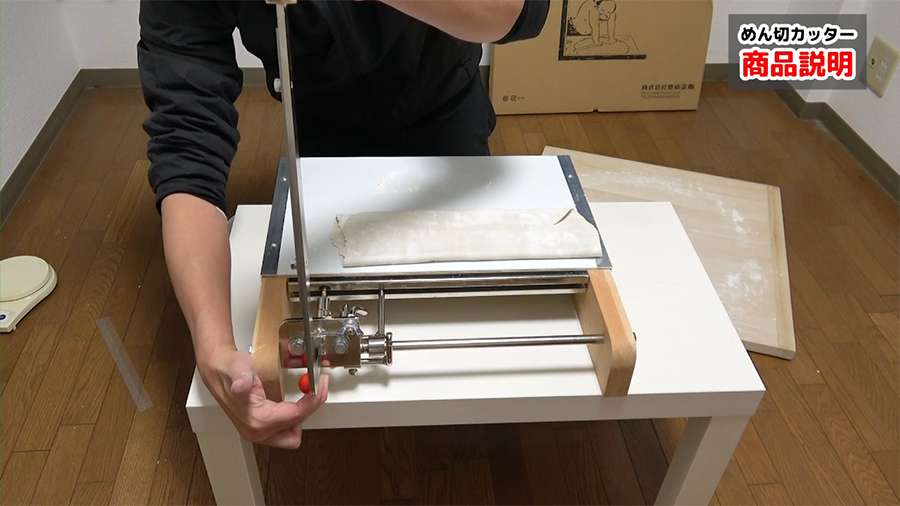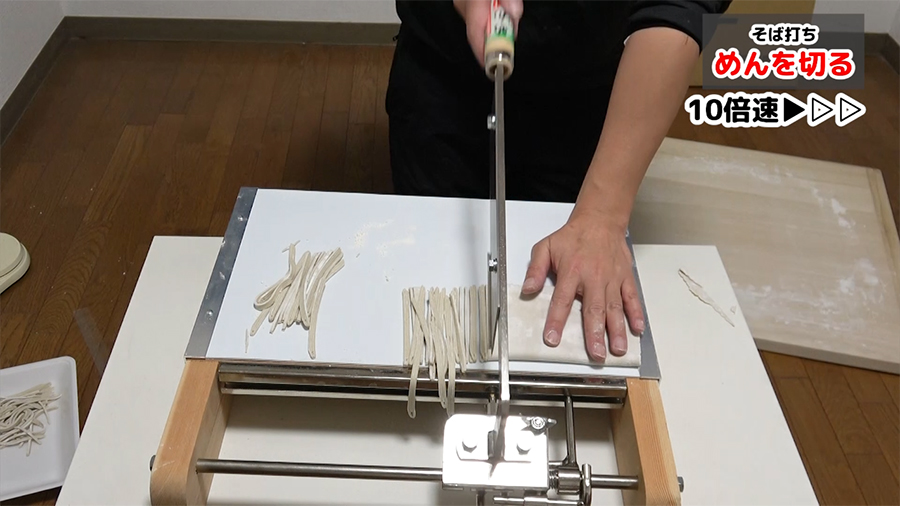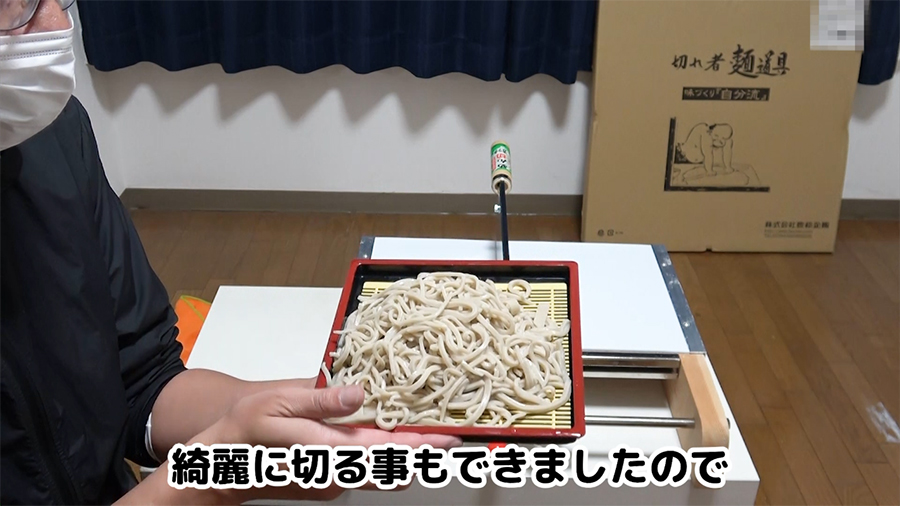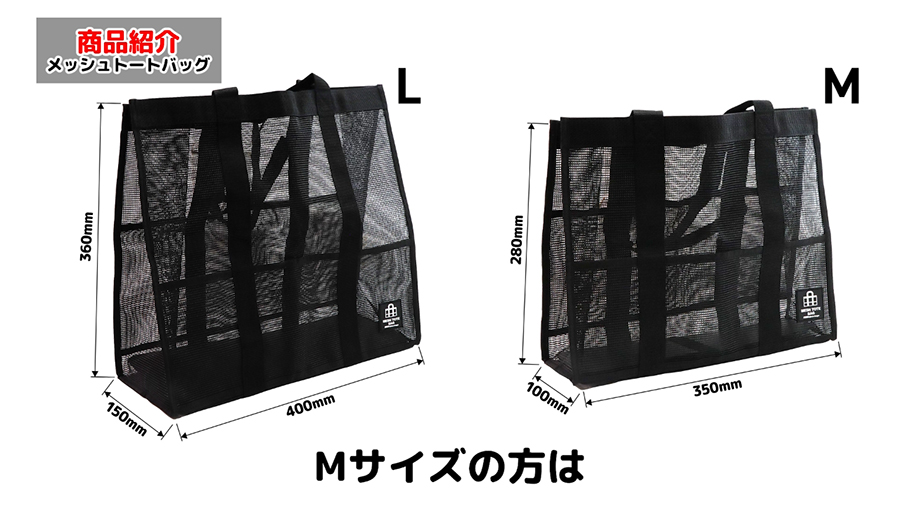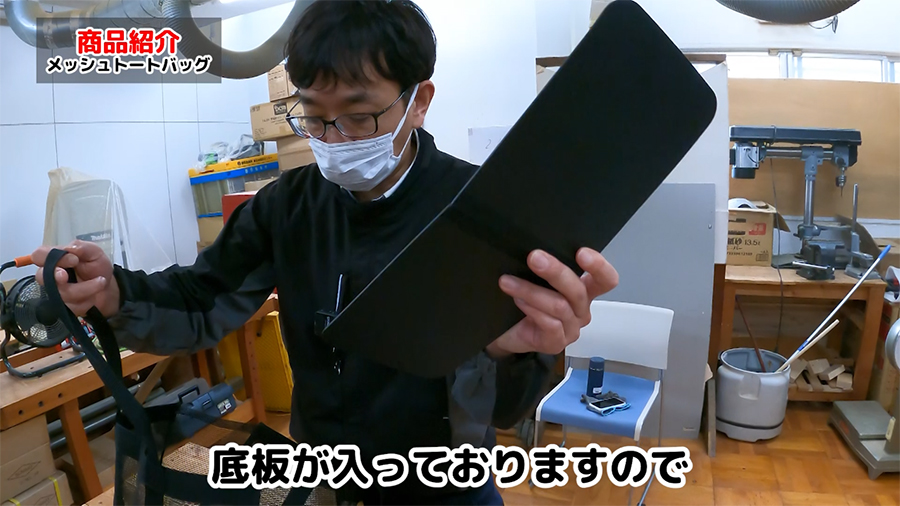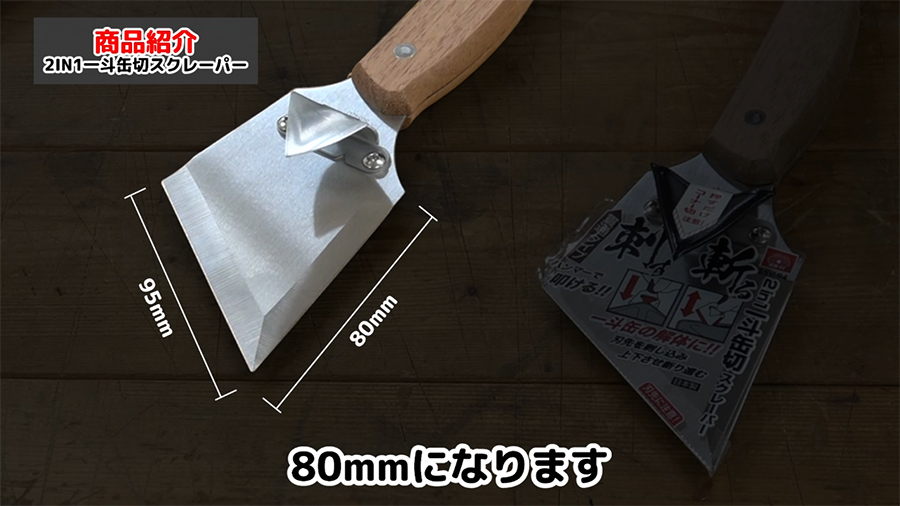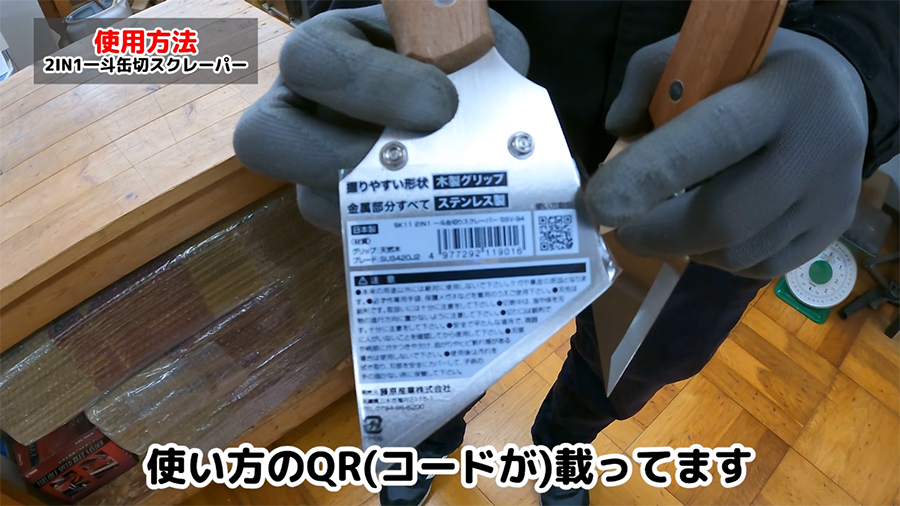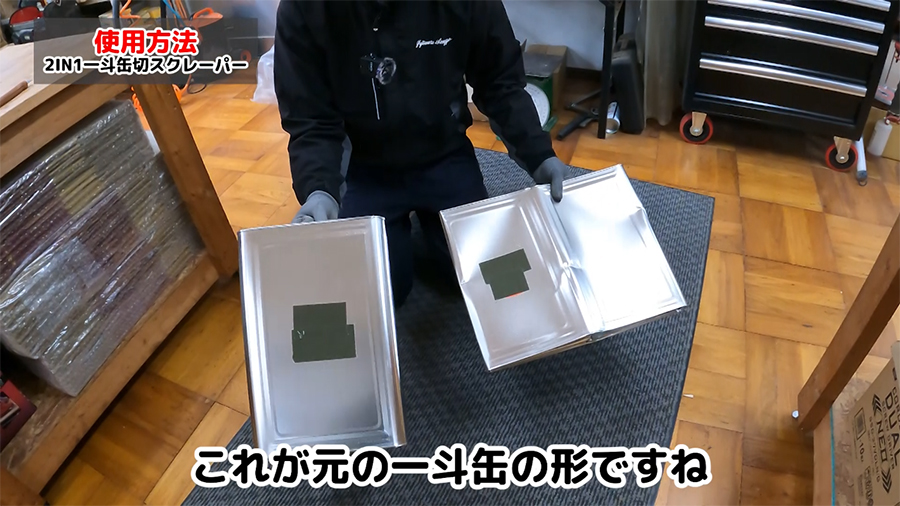本日は2026年新発売のエアコンプレッサーのサブタンクをご紹介します。

以前、ご紹介したサブエアータンクですが、原材料の高騰により値上がりしています。
しかしながら、現在までの出荷は好評を得ています。
そのため今回の新商品は原材料の見直しから行っています。

新商品は鉄タイプとアルミタイプがあり、それぞれ25Lと39Lがあります。
鉄タイプは25LがSAT-250IR、39LがSAT-390IR、アルミタイプは25LがSAT-250AL、39LがSAT-390ALです。
どちらも最高出力が1.0MPa、サイズは25Lが幅約575mm×高さ約405×奥行約240mm、39Lが横幅約645×高さ約460×奥行約280mmです。
重さは鉄タイプの25Lが約10.3kg、39Lが約13.4kg、アルミタイプは25Lが約5.7kg、39Lが約7.5kgとなっています。
アルミタイプは従来品と比べて軽量になっており、鉄タイプと比べるとわずか約1/2の重さとなっています。
エアコンプレッサー静音タイプのSW-045とSW-102を使って、タンクの空気充填にかかる時間を比較してみたいと思います。




①SW-045で25Lを溜める場合
タンクが満タンになるまでに5分55秒かかりました。

②SW-045で39Lを溜める場合
タンクが満タンになるまでに10分53秒かかりました。

③SW-102で25Lを溜める場合
タンクが満タンになるまでに4分15秒かかりました。

④SW-102で39Lを溜める場合
タンクが満タンになるまでに5分15秒かかりました。

SW-045は空気吐出量が15Lクラス、SW-102は空気吐出量が60LクラスなのでSW-102の方が早く空気が溜まりました。
サブタンクの使い方は簡単です。エアホースを空気取出し口(AかB)に差し込むだけです。
タンク直結の方の空気取出し口(A)に繋ぐと、そのまま空気が押し出されます。

圧力調整後の空気取出し口(B)に繋ぐと、空気取出し圧力計で設定した空気圧で取り出す事ができます。
指定した空気圧力でしか使えないエアーツール(エアタッカーやエアスプレーなど)を使う際に必要となります。
サブエアータンクを使うメリットとしては溜めておける空気の量が増えるので作業効率アップ、エアコンプレッサーの起動回数が減るのでモーターやスイッチの負担や電気代、騒音の軽減ができる事が挙げられます。
注意事項
・タンク内は空気が圧縮されていますので、くれぐれもエアホースの取り外しにはご注意ください。
・使い終わった後、そのままにしておくとタンク内に水が溜まりますので、必ずドレンコックから空気を全て抜くようにして下さい。


・エアコンプレッサーは最高圧力約1.0MPa以下のものをお使いください。
・タンク内に空気を溜める時に金属音のような異音が鳴りますが、問題ありません。
藤原産業のX(Twitter)でも役立つ情報を発信中です!!
ぜひこちらのフォローやいいねもお願いします
 Filed Under :
Filed Under :  1月.7,2026
1月.7,2026